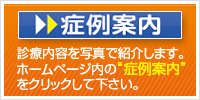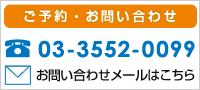歯科インプラントの導入から四半世紀以上が経過しました。近年インプラント治療の認知度は急激に向上しており平成23年歯科実態調査(厚生労働省)では、成人の40人1人(2.6%)はすでにインプラント治療を施しています。大学病院の専門外来はこの15年で患者数が6倍に増加しているようです。
それにともないインプラント治療による問題・不調患者数も増加してきているようです。

インプラントの問題
現在主流のチタン製スクリュータイプのインプラントの10年生存率は98.8%と非常に高い値が報告されています。
一方、件数ベースでのインプラント治療の問題も増加してきています。
問題の種類は、重篤度・時期によって3つに分類されます。
★手術時の異常事態
★手術後から上部に歯を取り付けるまでに起る問題
★上部に歯を取り付けた後に起こる問題

★手術時の異常事態
手術中に神経・血管等の損傷。鼻腔組織への埋入、手術中に起こる予期せぬ異常事態。
日本インプラント学会では最も重篤な医療トラブルと認定している。
これらの問題は重く、長期化する可能性がある。
しかし、CTレントゲンによる事前の診査によりこれらの問題は防げるようになってきています。
★手術後から上部に歯を取り付けるまでに起る問題
これは、オッセオインテグレーションというインプラント体表面と骨の表面の適合が得られず、術後にインプラントがグラグラになって抜ける問題です。
これは、手術の不手際でおこるものと考えられるが、最近のインプラント体の改良・術式の容易化によりこの問題は頻度が低下してきている。あまり重篤にならないとおもわれます。
★術後の上部に歯を取り付けた後に起こる問題
不衛生からインプラント周囲炎(歯槽膿漏みたいなもの)が起こる問題。
インプラントの長期残存に伴い顕在化してきた問題である。近年では、インプラント装着者の約半数に多少ないともみられるとの報告もあります。
また、高齢化、骨粗鬆症等などが、インプラント周囲炎のリスクファクターになると考えられています。

インプラント治療の問題点の予防
医療面接から診査、手術、メンテナンスまでの各作業を的確に行うことによって大部分の問題はコントロール可能と考えられます。インプラントを希望される場合、適切な医院で、適切な治療、適切な日々のお手入れを欠かさない事が重要です。
 2013.8.5 広瀬俊
2013.8.5 広瀬俊